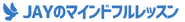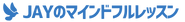「一人だと続かない…」を解決!協調性のある人のための習慣化メソッド
音声配信を文字起こしをしています
▽ ▽ ▽
おはようございます、JAYです。
昨日から「習慣化」についてお話ししています。
何かを継続したいとき、その方法については書籍やYouTubeなど、さまざまな情報がありますよね。
しかし、どの方法を試してもなかなかうまくいかないことがあると思います。
その理由について、昨日お話ししました。
実は、習慣化には「自分に合った法則」があるんです。
でも、世の中にある習慣化のノウハウは、多くの場合、著者がうまくいった方法や科学的に実証された一般的な手法を紹介しているものがほとんどです。
問題は、それが「誰にでも当てはまるわけではない」ということ。
性格タイプによって、向いている方法と向いていない方法があるんです。
だからこそ、自分の性格を知り、それに合った習慣化のメソッドを取り入れることが大切だと昨日お話ししました。
その際に活用できるのが、世界的に有名な「ビッグファイブ」という性格分類法です。
これは人の性格を5つの因子で分析し、自分に合った行動パターンを見つけるのに役立ちます。
昨日は、その中の「外交性」について解説しました。
もしあなたが社交的でエネルギッシュなタイプなら、ぜひこちらから昨日の音声をチェックしてみてください。
↓↓↓↓↓↓
ビッグファイブで考える!自分に合う習慣化の方法
そして今日は「協調性」についてお話しします。
この因子を持っている人が、どのように習慣を継続すればよいのか、具体的な方法をお伝えできればと思います。
昨日もお話ししましたが、ビッグファイブの性格分類において、一つの因子だけが絶対に当てはまるわけではありません。
人の性格はさまざまな状況や環境によって、5つの因子が複雑に作用しています。
そのため、「自分はこれだけ」と決めつける必要はありませんが、「確かに当てはまるな」と感じる部分があれば、習慣化の際に大いに役立ちますので、ぜひ参考にしてみてください。
ビッグファイブの5つの特性は以下の通りです。
- 外交性
- 協調性
- 誠実性
- 神経症傾向
- 開放性
今日は、この中の「協調性」についてお話しします。

協調性とは、その名の通り「誰かと協力することでモチベーションが上がる特性」です。
協調性が高い人は、周りの人との調和を大切にし、他者に合わせる力を持っています。
また、優しい性格の人が多く、繊細な一面も持ち合わせています。
たとえば、周りの人から「優しいね」とよく言われたり、「自分はちょっと繊細かも」と感じることがあるなら、あなたは協調性が高いタイプかもしれません。
この協調性を活かした習慣化の方法を知ることで、無理なく継続できるようになります。
今日は、その具体的な方法についてお伝えしていきます。
協調性が高い人が習慣化でつまずく4つの悩みとは?
協調性が高い人は、優しくて思いやりがあり、他人との調和を大切にする傾向があります。
これはとても素晴らしい特性ですが、習慣化をする上ではいくつかの悩みが生じることがあります。
今日は、協調性が強い人が抱えやすい習慣化の課題を4つご紹介します。
当てはまるものがあれば、ぜひこの後お伝えするメソッドを参考にしてみてください。

①自分のニーズを後回しにしてしまう
協調性が高い人は、他人の悩み事に耳を傾けたり、相手の期待に応えることに時間を使いがちです。
そのため、自分のための習慣を続ける時間が確保しにくくなります。
例えば、「毎日30分ランニングしよう」と決めていても、職場で「ちょっと手伝ってほしい」と頼まれて残業し、その結果習慣を続けられなくなることがよくあります。
気づけば習慣がすっかり途絶えてしまった…という経験、ありませんか?
②断るのが苦手でスケジュールが乱れる
協調性が高い人は「NO」と言うのが苦手です。
そのため、予定外の誘いや急な頼まれごとに巻き込まれやすく、結果として習慣化のルーティンが崩れてしまうことがあります。
「頼まれたら断れない」「つい予定を優先してしまう」といった性格が、継続の妨げになってしまうのです。
③モチベーションが他人依存になりがち
協調性の高い人は、周りからの応援や承認があると頑張れるタイプですが、逆に「誰にも見られていない」「褒められない」と続けられなくなることがあります。
例えば、「みんながいるからジムに行けるけど、一人だと続かない」「SNSで報告すると頑張れるけど、誰にも言わないとやる気が出ない」といったことが起こりやすいのです。
④完璧主義でプレッシャーを感じやすい
「失敗したらどうしよう」「誰かに迷惑をかけるんじゃないか」と考えてしまい、プレッシャーを感じすぎてしまうこともあります。
最初は意欲的に始めたものの、「ちゃんとできなかったら意味がない」「完璧にやらなきゃ」と考えるうちに疲れてしまい、結果的に習慣をやめてしまうことがあるのです。
これらの悩みに心当たりがある方は、次にお伝えする習慣化のメソッドがとても役に立つと思います。
協調性の高さを活かして習慣を続ける6つの方法
協調性が高い人が習慣を継続するためには、「環境を工夫する」 ことがとても大切です。
なぜなら、こうしたタイプの人は誰かと一緒に取り組むことでモチベーションが上がりやすい からです。
ここでは、習慣化を助ける具体的な方法を6つご紹介します。

①グループ活動やペアでの取り組みを取り入れる
一人で続けるのが苦手な場合は、バディを作る のがおすすめです。
例えば、ジムなら友達と一緒に行く、勉強なら勉強会を開くなど、「誰かと一緒にやる」仕組みを作ることで、自然と継続しやすくなります。
②他者への貢献を意識する
協調性が高い人は、「誰かの役に立つ」と思うと頑張れる 傾向があります。
例えば、家族のために毎日料理をする、ボランティア活動に参加するなど、誰かの喜びにつながる形で習慣を作ると続けやすくなります。
これを通じて「自分は継続が得意なんだ」という自信も生まれ、習慣化がさらに加速します。
③他人からのフィードバックを受ける
SNSで進捗をシェアして友達からコメントをもらったり、目標を周囲に宣言するのも効果的です。
「宣言効果」 と呼ばれるように、周りに公言することでやる気が続きやすくなります。
④自分のための時間を意識的に作る
協調性が高い人は、つい他人を優先しがち。
でも、自分のニーズも大切にしましょう。
例えば、「1日1時間は必ず自分の時間を確保する」 など、意識的に自分のための時間を確保することが大切です。
⑤小さな成功を他人と共有する
他人との共有が励みになるタイプの人は、週に1回でも家族や友達に進捗を報告する のがおすすめです。
「今週は3日間ランニングできた!」「毎日10分読書できた!」といった小さな達成を誰かに伝えるだけで、モチベーションが高まります。
⑥自分に優しい言葉をかける
協調性が高い人は、他人に優しい反面、自分には厳しくなりがち です。
でも、習慣を続ける上で大切なのはセルフコンパッション(自分への思いやり)。
失敗しても「次は頑張ろう」と前向きに考え、決して自分を責めすぎないようにしましょう。
協調性の高さは、習慣化の妨げになることもありますが、工夫次第でむしろ**「強み」に変えられます**。
ぜひ、今日から試してみてくださいね。
今日もあなたにとってマインドフルな一日になりますように。
いってらっしゃい!
マインドフルネス×潜在意識勉強会はコチラ
↓
ご案内ページへ
※紹介者名欄にJAYブログとご記載いただくと無料で参加できます
JAYへの質問・相談はこちら
↓
フォームページへ