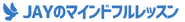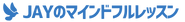「自分の豊かさの定義」を見つける:他人と比べず、自分らしく生きる方法
音声配信を文字起こしをしています
▽ ▽ ▽
おはようございます、JAYです。
今日もベトナムの朝を散歩しながらお話ししていきたいと思います。
さて、今日は以前少しお話しした「豊かさの定義」について、改めて考えてみたいと思います。
以前もお伝えしましたが、豊かさの定義を自分の中でしっかりと持つことで、他人と比較することがなくなり、誰かの評価を気にすることも少なくなっていきます。
これは「ミッションステートメントを作る」という考え方にも通じるものがあります。
ミッションステートメントとは、『7つの習慣』という本でスティーブン・コヴィー博士が提唱している概念です。
これは、自分の軸を明確にし、他人の評価や期待に左右されずに生きるための指針となるものです。
つい他人の目を気にしてしまいがちですが、自分が本当にどうしたいのか、どんな人生を送りたいのかを考え、それに沿って行動していくことが大切なのです。
以前の配信でもお話ししましたが、豊かさの定義のひとつとして「楽しいかどうかで判断する」という視点があります。
何かを選択するとき、そこに楽しさを感じられるかどうかを基準にしてみる。
そうすることで、より自分らしい豊かな人生が築けるのではないでしょうか。
このテーマについては、以前の配信でより詳しくお話ししていますので、興味があればそちらも参考にしてみてください。
こちらになります↓
幼少期の経験が豊かさの定義を決める?潜在意識の影響とは
さて、今日は「豊かさの定義」とは何なのかについて、さらに深掘りしていきたいと思います。
僕たちは幼少期に、自分の判断軸を決めると言われています。

およそ7歳頃までに、固定観念が潜在意識の中で形成されるとされており、その頃の原体験をもとに
「自分はこういう人間だ」
「こうあるべきだ」
という意識が作られるのです。
この固定観念は、周囲の大人たちの言葉がけによって大きく影響を受けます。
親や先生など身近な人からの言葉が、知らず知らずのうちに潜在意識に刻まれ、それが「自己観念」となります。
これは「セルフイメージ」とも呼ばれます。
例えば、子供の頃に否定され続けた経験があると、「自分は否定される人間だ」という固定観念が出来上がります。
すると、無意識のうちに自己否定が癖になり、何かうまくいかないことがあるたびに「自分が悪い」と責めてしまうのです。
そして、この固定観念こそが、自分の人生の豊かさの定義を形作っていくのです。
頑張ることが豊かさ?他人軸に縛られる思考の落とし穴
例えば、子供の頃に「頑張らないとうまくできません」と親に言われ続けたとします。
そうすると、「頑張ること」が自分にとって非常に重要な価値観になっていきます。
「頑張って成果を出しなさい」
「周りの人から評価を得なさい」
といった考えが自分の中に根付き、やがてそれが自分の人格を作る基盤になってしまうのです。
こうした価値観を持つと、誰かからの評価がないと自分の価値を感じられなくなります。
自分が本当はどうしたいのかよりも、「どうすれば評価されるのか」が判断基準になってしまう。
そして、他人の評価を得ることこそが豊かさなのだと、無意識のうちに思い込んでしまうのです。

こうなると、他人軸で生きるようになり、周囲の評価が気になって仕方がなくなります。
「誰かより優れていなければならない」という考えが根付き、無意識のうちに自分の豊かさを「他人と比べて自分のほうが優れていること」として定義してしまうのです。
その結果、常に誰かと比較するようになります。
たとえば、SNSで自分と似たようなことをしている人を見つけては、自分と比較し、相手が自分よりも成果を出していると落ち込んだり、逆に自分のほうができていることを探して安心したりします。
そんな尺度で世界を見てしまうのです。
でも、この「豊かさの定義」は潜在意識の中にあるため、自分では気づきにくいものです。
「あなたにとっての豊かさとは?」と聞かれても、「人と比べて自分が優れていることです」とはなかなか言語化できません。
ただ、日々の中で無意識に比較し、そこから感情が生まれているのです。
では、どうすればこの無意識の比較から抜け出せるのでしょうか?
そのヒントは、自分のネガティブな感情を観察することにあります。
自分がどんなときにネガティブな感情を抱くのか、どんな出来事が引き金になっているのかを振り返ってみる。

そうすることで、自分の思考の癖に気づくことができます。
私たちは誰しも、頭の中で絶えずおしゃべりをしています。
この「頭のおしゃべり」こそが、思考の癖を生み出すものです。
もし自分が「ネガティブな性格だ」と感じているとしたら、それは性格ではなく、ネガティブに物事を捉える思考の癖があるということ。
そう考えると、変えることもできるのではないでしょうか?
ポジティブとネガティブは性格ではなく思考の癖である
ポジティブな人とはどんな人でしょうか?
「自分はポジティブだ」と思っている人、もしくは周りから「あの人はポジティブだよね」と言われる人。
実は、その違いは単に思考の癖の違いにすぎません。
ポジティブな人は、頭のおしゃべり——つまり、日々の思考の流れが前向きな傾向にある。
それだけのことなのです。

つまり、「ネガティブな性格」や「ポジティブな性格」といったものは本来なく、ただ単に思考の癖が前向きか後ろ向きか、それだけの違いなのです。
楽観的か悲観的かという違いがあるだけ。
最近では、脳科学や心理学、特に認知心理学の研究が急速に進んでいます。
なぜなら、これらの研究がAIの発展に大きく貢献しているからです。
特に言語モデルAIを開発する際には、人間の認知の仕組みや思考のパターンが参考にされるため、認知心理学の分野はますます注目を集めています。
こうした研究が進む中で、自分の人生を思い通りに生きられる人、つまり人生を豊かにしている人の特徴が明らかになってきました。
それは、「前向きな思考の癖を持っている」ということです。
一方で、悲観的に物事を捉えやすい人は、ネガティブな言動をしやすく、結果として自分の望む方向へ進みにくくなる。
これは、私たちが子供の頃に親や周囲の大人たちから受けた教育や言葉が大きく影響しています。
特に昭和の時代には、現在の科学的な知見とは異なる価値観が主流でした。
私自身、昭和生まれですが、父は戦前生まれの世代で、いわゆる“頑固じじい”に育てられました。
当時は
「頑張ること」
「ストイックに努力すること」
「厳しく育てること」
に価値が置かれていたのです。

そのため、自尊感情を育むよりも、
「足りない部分を補うために努力する」
「未来のリスクを先取りして慎重に行動する」
ことが重要視されていました。
それが結果的に、「自分を肯定する力」よりも「自己否定や悲観的な思考の癖」を強化することにつながったのです。
しかし、今では科学的に「自尊心を育む教育」が良いとされています。
つまり、私たちは過去の教育によって無意識に身につけた思考の癖に気づき、意識的に変えていくことができるのです。
豊かな人生を送るために、まずは自分の思考の癖を観察し、少しずつ前向きな方向へシフトさせていくことが大切なのかもしれません。
過去の教育からの解放、思考の癖は変えられる
かつての教育では、「厳しさ」や「ストイックさ」が美徳とされ、前向きな思考よりも悲観的に物事を捉えることが求められる場面が多くありました。
私自身も幼い頃、少しでも反抗的な態度をとると正座をさせられたり、頬を打たれたりと、今で言う「体罰」のような指導を受けながら育ちました。
そうした環境の中で、
「頑張らないといけない」
「誰よりも優れていないと価値がない」
といった観念に縛られ、強いプレッシャーを感じながら生きていました。
しかし、大人になってから認知心理学や催眠療法を学び、それらの資格を取得する過程で、自分の思考の癖を客観的に捉え、変えていくことができるのだと気づきました。
ネガティブな思考の癖というのは、単なる「癖」であり、固定された性格ではないのです。
そのため、自分を「ネガティブな人間」と決めつける必要はなく、意識的に変えていくことができるのです。
もちろん、一朝一夕に変わるものではありません。

しかし、少しずつでも前向きな思考の習慣を身につけることで、人生の捉え方そのものが変わっていきます。
今後は、思考の癖を前向きに変える具体的な方法についてもお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
今日は「自分の豊かさの定義」についての話から少し逸れてしまいましたが、自分にとっての豊かさとは何かを見つめる時間を持つことは、とても大切なことです。
誰かと比べるのではなく、自分自身にとっての豊かさを定義し、それに向かって歩んでいく。
たった一度きりの人生を、あなたらしく彩っていきましょう。
さあ、新しい一日をスタートさせましょう。
今日も素敵な一日をお過ごしください。
いってらっしゃい。
マインドフルネス×潜在意識勉強会はコチラ
↓
ご案内ページへ
※紹介者名欄にJAYブログとご記載いただくと無料で参加できます
JAYへの質問・相談はこちら
↓
フォームページへ