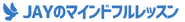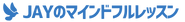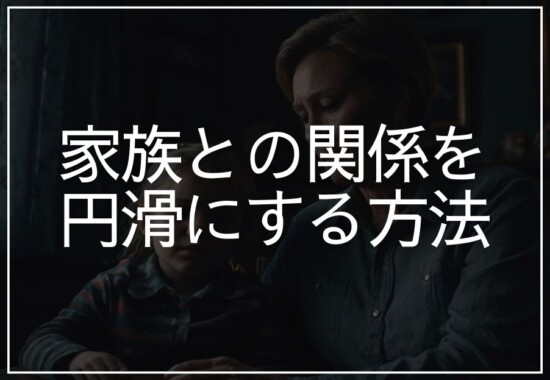親との関係が人格を決める?回避者タイプの形成要因を解説
音声配信を文字起こしをしています
▽ ▽ ▽
おはようございます、JAYです。
今日も引き続きアダルトチルドレンについてお話ししていきましょう。
ここ数日間、アダルトチルドレンのタイプ別分類をお伝えしながら、それぞれのタイプに合った改善方法や対策をシェアしています。
今日はその第3回目ですね。
昨日は自己犠牲タイプ、一昨日は完璧主義タイプ、そしてその前の日にはアダルトチルドレンの全体像についてお話ししました。
今日は「回避者タイプ」について取り上げていきます。
アダルトチルドレンにはいくつかのタイプがあり、明日は「依存者タイプ」、明後日は「感情抑圧タイプ」、その次の日には「攻撃者タイプ」についてお届けする予定です。
全部で6つのタイプに分類して解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
さて、回避者タイプについてですが、アダルトチルドレンのタイプ分けは、必ずしも1つのタイプだけに当てはまるわけではありません。
「私はこのタイプに分類される」と決めつけるのではなく、「この部分は確かに回避者タイプっぽいけれど、依存者タイプの要素もあるな」というように、いくつかのタイプが混ざっていることもよくあります。
グレーゾーンがあるのは当然なので、自分に当てはまりそうな部分を参考にしていただければと思います。
それでは、回避者タイプの特徴について詳しく見ていきましょう。
もし「自分はこのタイプに近いかも」と感じたら、ぜひ今日のお話をじっくり聞いてみてください。
親密な関係を築けない理由とは?回避者タイプの心理を解説
回避者タイプとは、主に対人関係を避ける傾向が強い人のことを指します。
人との深い関わりを恐れ、親密な関係を築くことに抵抗を感じる特徴があります。
その結果、日常生活や人間関係に大きな影響を与えてしまうこともあります。
では、具体的にどのような特徴があるのでしょうか?

1. 対人関係の回避
回避者タイプの人は、他人との親密な関係を築くことを恐れます。
そのため、自己開示や自分の考えや感情を表現するのが苦手です。
友達やパートナーとの距離を保とうとし、表面的な会話にとどまることが多いです。
例えば、親しい友人と話していても、個人的な話題を避けて天気やニュースなどの無難な話題に終始してしまうことがあります。
2. 感情の抑圧
自分の感情を表現するのが苦手で、感情を抑え込むことが習慣になってしまいます。
怒り、悲しみ、喜びなどの感情を他人に見せず、できるだけ隠そうとする傾向があります。
例えば、辛い出来事があっても「大丈夫」と言ってしまい、本当の気持ちを打ち明けられないことがよくあります。
3. 孤立感と孤独
他人との繋がりを避けるため、孤立感や孤独感を抱えやすくなります。
社交的な場に行っても、周りに溶け込むのが難しく、隅の方で静かに過ごすことが多くなりがちです。
4. 信頼の欠如
回避者タイプの人は、他人を信頼することが難しく感じます。
「裏切られるかもしれない」という不安が強く、過去の経験から人に頼ることや感情を開示することを避けがちです。
例えば、困ったことがあっても助けを求めるのをためらい、一人で解決しようとする傾向があります。
5. 自己防衛的な行動
感情的な傷を避けるために、自己防衛的な行動をとります。
他人との関係においてリスクを避け、距離を保つことで自分を守ろうとします。
その結果、新しい友達を作ることを避けたり、既存の関係も浅いまま維持しようとしてしまうことが多いです。
これらの特徴が、回避者タイプの人に見られる傾向です。
もし「自分に当てはまるかも」と感じたら、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ感情を抑えてしまうのか?回避者タイプの背景を探る
回避者タイプの人は、幼少期の家庭環境に大きな影響を受けています。
特に、親との関係性や家庭の雰囲気が、感情の抑圧や対人関係の回避につながる要因となります。
ここでは、回避者タイプになりやすい環境について詳しく見ていきます。
1. 感情的に利用不能な親
子供にとって「利用不能な親」とは、感情的に冷淡で、子供の感情的なニーズに応えない親のことを指します。
例えば、親が仕事や自分の問題に忙しく、子供の話を聞かない家庭で育つと、子供は「感情を表現しても無視される」と学んでしまいます。
その結果、感情を抑えることが習慣になってしまうのです。
2. 虐待やネグレクト(育児放棄)
身体的・精神的な虐待やネグレクトを経験した子供は、他人を信頼することができず、感情を抑え込むことで自己防衛するようになります。
例えば、親からの暴力や無視をされ続けると、「感情を表に出すと危険だ」と学習し、感情を隠すクセがついてしまいます。
3. 過干渉や過保護
親が過度にコントロールし、子供の自立を妨げる環境も、回避者タイプの形成に影響します。
・常に行動を監視される
・自分の意見を押し付けられる
・親の期待に応えなければならない
このような環境では、子供は自分の感情や欲求を無視することを学び、自己表現が苦手になります。
4. 親との関係が人格に与える影響
実家の両親と会うと、まるで別人格になってしまう……そんな経験はありませんか?
例えば、親が子供の意見を一方的に否定し、コミュニケーションが成り立たない家庭では、子供は「自分の感情を出しても意味がない」と感じるようになります。
親が話を一方的に進め、自分の話に持っていくタイプだと、子供は「どうせ聞いてもらえない」と思い、感情を抑え込むクセがつきます。
5. 親の離婚や家庭内不和
親が頻繁に喧嘩をしていたり、離婚を経験したりすると、子供は安全な環境を失い、対人関係への不信感を抱きやすくなります。
幼少期の子供にとって、家庭は「世界のすべて」です。
その家庭が不安定であればあるほど、「人との関わりは危険だ」と学習し、回避傾向が強まるのです。
幼少期の家庭環境が安心できるものであれば、人は自然と他人を信頼し、感情を表現することができます。
しかし、親が冷淡だったり、過干渉だったりすると、子供は「感情を出さない方が安全だ」と学びます。
こうして身につけた防衛本能は、大人になると逆効果になり、健全な人間関係を築くことを難しくしてしまうのです。

幼少期の影響と向き合う:人間関係を築くための3つのステップ
感情を抑え込む習慣を改善し、人との関係を築くためにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは3つの具体的な方法を紹介します。
1. 小さなステップで人間関係構築の練習をする
まずは、信頼できる人と短時間の交流を持つことから始めましょう。
例えば、週に1回、5分だけでもいいので、友達と電話をしてみる。
その中で少しずつ、自分の気持ちを話してみるのです。
また、職場の同僚との雑談の中で、自分の好きな映画や本について話すのもよい練習になります。
最初は軽い話題から始め、慣れてきたら少しずつ深い話に進めていくとよいでしょう。
大切なのは、小さな成功体験を積むことです。
「話してみたら意外と受け入れてもらえた」という経験を重ねることで、他人とのつながりに対する不安を和らげることができます。
2. 感情の共有を意識する
次に、自分の感情を表現する練習をしてみましょう。
これは、他人との会話の中で実践することもできますが、最初のステップとして「感情日記」をつけるのもおすすめです。
例えば、
・今日は〇〇があって、すごく嬉しかった。
・仕事でミスをしてしまい、とても落ち込んだ。
・友達の言葉に励まされて、少し気持ちが軽くなった。
このように、具体的な出来事とともに感情を書き出すことで、自分の内面と向き合う習慣がつきます。
また、信頼できる友人がいれば、電話や対面で「今日はこんなことがあって、こんな気持ちになったんだ」と話してみましょう。
感情を共有することで、他人とのつながりを実感しやすくなり、孤独感が軽減されることがあります。
3. 安心感を育むためにカウンセリングを活用する
最後に、専門家の力を借りることも有効な手段です。
日本ではまだカウンセリングの利用が一般的ではありませんが、海外では日常的に活用されています。
カウンセリングを受けることで、自分の感情や過去の経験を整理し、より客観的に捉えられるようになります。
また、インナーチャイルドを癒すことで、幼少期の影響を和らげることもできます。
もし「誰かに話を聞いてほしいけど、友達や家族には話しづらい」と感じる場合は、カウンセラーや心理セラピストを頼ることを検討してみてください。
特別なことではないし、自分だけではない
アダルトチルドレンという概念に当てはまるかもしれないと感じても、それは特別なことではありません。
同じような経験をしている人はたくさんいます。
大切なのは、「自分だけではない」と知ること。
そして、小さな一歩を積み重ねながら、自分自身と向き合い、少しずつ前に進んでいくことです。
あなたの一日が、穏やかで素敵なものになりますように。
いってらっしゃい!
マインドフルネス×潜在意識勉強会はコチラ
↓
ご案内ページへ
※紹介者名欄にJAYブログとご記載いただくと無料で参加できます
JAYへの質問・相談はこちら
↓
フォームページへ