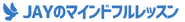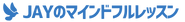過去の抑圧を癒す:感情を解放するための実践的アプローチ
音声配信を文字起こしをしています
▽ ▽ ▽
おはようございます、JAYです。
さて、今日はアダルトチルドレンについての解説を続けていきます。
今回で5日目になりますね。
今日は「感情抑制者タイプ」のアダルトチルドレンについて、その特徴と対処法をお話ししていきます。
感情抑制者タイプとは、感情を抑え込み、表現することが苦手な特性を持つ人々のことを指します。
子供の頃に感情を表に出さず、隠すことを学び、大人になってもその影響が続いてしまう。
そんなパターンですね。
まずは、このタイプの方の特性についてお伝えします。
もし「自分に当てはまるかも」と思ったら、ぜひ最後まで聞いて、対策もチェックしてみてくださいね。
「自分の気持ちがわからない…」感情抑制者タイプとは?
感情を処理したり、表現したりすることが苦手な人には、いくつかの共通する特徴があります。
ここでは、主なポイントを紹介していきます。
1. 感情の抑圧
自分の感情を意識的に抑え込む、または無意識的に押さえつけてしまう傾向があります。
表に出せない、あるいは出さない選択をしてしまうのです。
例えば、悲しいことがあっても涙を見せず、「平気」と振る舞うことが多いのが特徴です。
2. 感情表現の苦手意識
自分の気持ちを言葉や行動で表現するのが難しく、他人に伝えることを避ける傾向があります。
例えば、本当は怒っているのに「大丈夫」と言ってしまい、内心では大きなストレスを抱え込む。
こうしたパターンが日常的に続くことで、自分の気持ちが伝わらず、周囲との関係にも影響を及ぼすことがあります。
「ある程度は誰にでもあること」と思うかもしれませんが、それが日常生活に支障をきたしていたり、「もしかしてこれが原因で人生がうまくいかないのでは?」と感じるようなら、一度向き合ってみる価値があるかもしれません。
3. 内面の葛藤
感情を抑え続けることで、内面ではストレスや不満が蓄積しやすくなります。
そして、それが限界に達すると、突然爆発してしまうことも。たとえば、長い間我慢していたのに、ある日突然怒りが爆発して周囲が驚いてしまう、といったことが起こりやすいのです。
逆に、感情を抑えすぎた結果、無気力になってしまうケースもあります。
4. 感情への無自覚
自分が何を感じているのか、そもそも分からなくなってしまうこともあります。
例えば、嬉しい出来事があっても、その感情を意識できず淡々と過ごしてしまう。
あるいは、「本来なら嬉しいはずのシチュエーションなのに、なぜか気持ちが動かない…」と感じることがあるかもしれません。
5. 対人関係での距離感
感情表現が苦手なため、他人との深い関係を築きにくい傾向があります。
友人や家族との会話でも、感情的な話題を避け、表面的なやり取りにとどまることが多いのです。
これは、以前紹介した「回避者タイプ」とも共通する部分があります。
人と人の信頼関係を築くには、感情を表現し、相手の気持ちを読み取る力が必要です。
しかし、それが苦手なため、深い人間関係を築きにくくなってしまうのです。

もし「自分に当てはまるかも」と思ったら、ぜひ次に紹介する対策を試してみてくださいね。
あなたが一人で悩んでいるわけではありません。
今は相談できる場所も増えていますし、少しずつでも自分の気持ちに気づき、表現する練習をしていくことが大切です。
幼少期の経験が感情表現を難しくする理由
幼少期の家庭環境が、感情の抑圧につながる大きな要因となることが多いです。
親からの言葉や態度が、子どもに感情を抑えることの必要性を無意識に刷り込んでしまうのです。
①感情を否定され続けた経験
例えば、「泣くな」「我慢しなさい」と繰り返し言われると、子どもは「感情を出すのは悪いこと」と学びます。
泣くと叱られる、無視されるといった経験があると、「感情を表に出さない方が安全だ」と感じるようになります。
②機能不全な家庭環境
家庭内にアルコール依存症や精神疾患を持つ親がいる場合、不安定な環境で育った子どもは、自分の感情を抑えることで身を守ろうとします。
親の怒りを避けるために、気持ちを押し殺す習慣がついてしまうこともあります。
③感情的なネグレクト(無視される経験)
親が子どもの感情に対して無関心であると、子どもは「どうせ訴えても反応がない」と感じ、感情表現をやめてしまいます。
悲しみを訴えても何の反応もない環境では、感情を内側に閉じ込めるようになり、「感情を出しても意味がない」と学んでしまうのです。
④過度な期待や役割の押し付け
「良い子でいること」や「家庭を支えること」を強く求められると、感情よりも責任を優先するようになります。
例えば、兄弟の世話をしなければならないヤングケアラーのような経験をすると、「自分の気持ちを我慢して役割を果たすことが大事」と考えるようになり、感情を後回しにするクセがついてしまいます。

僕自身も、かつては親から感情を抑圧されて育ちました。
しかし、それがどれほど影響を及ぼすのかを学び、自分の子どもには同じ思いをさせたくないと考えるようになりました。
例えば、僕の小学3年生の長女は「悔しい」気持ちを怒りに変えて表現することがあります。
兄弟喧嘩の時や、妻に対して怒る時もあります。
そんな時、僕は「なんで怒ってるの?」ではなく、「腹立つよね」と共感の言葉をかけるようにしています。
そして、「おいで」と言って抱きしめてあげると、怒りの感情がスッと落ち着いていくのが分かります。
これは、どんな感情でも同じです。
「なんでそんなことで泣くの?」と否定するのではなく、「そうか、悲しいよね」と受け止めてあげることで、子どもは安心感を得ることができます。
僕自身、過去に感情を抑圧されていたからこそ、今は「共感してあげること」の大切さを実感しています。
もし、自分が幼少期に感情を抑えて生きてきたと感じるなら、自分の気持ちを少しずつ受け入れ、表現する練習をしてみることが大切かもしれません。
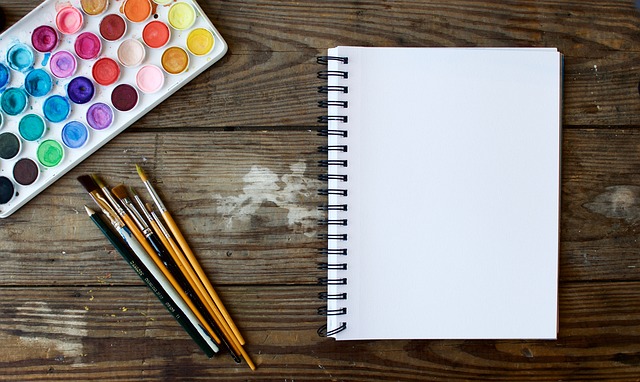
自分の感情を理解し、表現する方法
感情を抑え込みがちな人に向けて、感情を理解し、表現するための3つの改善策をご紹介します。
①感情の識別
感情を理解するために、日々の感情を言葉にする練習をしてみましょう。
例えば、感情日記をつけることで、自分がどんな感情を抱いているのかを確認することができます。
・1日1回、感情を言語化してノートに書き出してみることから始めてみましょう。
・「今日は仕事でミスして悔しかった」「友達と話してウキウキした」など、具体的な感情を表現します。
・感情の強さを1から10で評価すると、さらに感情を認識する力が育まれます。
②表現の場を持つ
言語ではなく、非言語的な方法で感情を表現することも大切です。
・アートセラピーや音楽療法
例えば、その日の気分を絵や音楽で表現することができます。
絵を描いたり、楽器を演奏したりすることで、言葉では表現できない感情を外に出すことができます。
・カラオケやダンス
歌やダンスを通じて、感情を強く表現するのも一つの方法です。
カラオケで自分の気分にぴったりな曲を歌うことで、感情を解放できます。
・自分に合った方法を見つける
例えば、ストレスを感じたときに粘土を握りつぶす、もしくはギターや歌を練習することも効果的です。
自分に合った表現方法を見つけて、感情を開放しましょう。
③マインドフルネス
マインドフルネスは、感情に気づくために非常に効果的です。
・瞑想や体を動かしながらのマインドフルネス
ヨガやストレッチなど、体に意識を向けながら行うことでも、今の自分の感情に気づくことができます。
・今ここに意識を向ける
深呼吸やリラックスを通じて、今この瞬間に意識を向けることが大切です。思考が出てきても、動作に意識を戻すことで、今の感情に気づくことができます。
・観察することが重要
自分の感情を否定するのではなく、ただ観察することが大切です。これにより、自分の感情を受け入れる力が高まります。
これらの方法を実践することで、感情をより深く理解し、表現することができるようになります。
みんなの感情には背景がある、理解と表現が大切
感情を抑え込む背景には、多くの人が経験してきた理不尽な出来事や、過去の記憶が影響しています。
例えば、僕自身も子供の頃、少しでも反抗的な態度を取ると、親からビンタされることがありました。
特にドラクエ3にハマっていたとき、ゲームに没頭していると、突然部屋に入ってきた親がファミコンの電源を抜くなどの行動をして、悔しさと怒りでいっぱいになったことがあります。
その時、親の前で怒りを表現するとまた怒鳴られるのが怖かったので、心の中でその感情を必死にこらえた経験が今も残っています。
こうした過去の経験が、今でも感情を抑えることに影響していることが分かります。
感情を抑えるというのは、当時は自分を守るための手段でしたが、今となってはそれが無意識のうちに行動に表れることがあります。
しかし、みんな多少なりとも似たような経験をしているはずです。
だからこそ、自分だけが特別な存在ではなく、誰しも過去に影響を受けていることを理解することが大切です。
自分の感情に気づくことや、表現することは、過去の経験を癒し、解放するための第一歩です。
感情を抑え込むことが習慣になっている人は、それが「普通」だと感じがちですが、それを乗り越えて表現していくことが、心の自由を取り戻す手助けになります。
今日も、あなたにとってマインドフルで素敵な1日が訪れることを願っています。
マインドフルネス×潜在意識勉強会はコチラ
↓
ご案内ページへ
※紹介者名欄にJAYブログとご記載いただくと無料で参加できます
JAYへの質問・相談はこちら
↓
フォームページへ