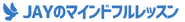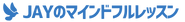マインドフルネスは怪しい?宗教観を超えた新しい心のトレーニング
音声配信を文字起こしをしています
▽ ▽ ▽
おはようございます、JAYです。
今日はですね、マインドフルネスに関するご質問をいただいておりましたので、そちらについて解説していきたいと思います。
いただいたご質問はこちらです。
この前本屋さんでマインドフルネスの本を立ち読みしてみたんですけども、内容がなんとなくスピリチュアルっぽく感じてしまって一歩踏み出すことをためらってしまいました。特に『今この瞬間に集中する』とか『心の平穏を保つ』といった言葉が少し宗教的なものと結びついているように感じてしまって、私は普段からそういった精神的な話にあまり馴染みがなく、どこかうさんくさいと思ってしまう部分がある。また、昔、瞑想が宗教の儀式の一部だと聞いたことがあって、それもあってかマインドフルネスには手を出しづらいイメージを持っています。実際にやってみたら思っているほど宗教的なものではないのかもしれませんが、初心者の私でも気軽に始められるものなのでしょうか。それとも、ある程度そういう考え方や受け入れ方ができていないと難しいと感じますでしょうか。もし抵抗を感じる私のような人でも取り組める方法があれば教えていただきたいです。
ということで、マインドフルネスや瞑想と聞くと「うさんくさいな」と思ってしまうという声。
昔はよく聞きましたが、最近あまり聞かなくなりましたね。
でもまあ、いらっしゃるでしょうね。
日本人がマインドフルネスを怪しく感じる理由
うさんくさいと感じてしまう方がいらっしゃる理由、それは宗教の文脈が関係しているからですね。
また、日本人は特にそう感じてしまう傾向があります。
これは海外の方と話しているとよくわかります。
例えば、海外では瞑想のことを「メディテーション」と言いますが、多くの人が「いいものだよね」と受け入れています。
一方、日本人の場合、「瞑想」と聞くと、どこか怪しく感じてしまう傾向があるんです。
この背景にはいくつかの要因があります。
一つは、宗教に対する怪しさや、瞑想そのものへの不信感です。
これは戦後、GHQが日本を統治し、長期的な植民地化を目指す中で行われた政策が関係しています。
その中で、日本国内で使えない言葉や、弾圧された事柄が多くありました。
神道や仏教といった日本人の精神的な強さを支えていた要素も、その対象の一つとされたのです。

その結果、日本では無宗教化が進み、宗教そのものに対してネガティブなイメージを持つようになったとされています。
また、宗教や政治に関する意見を述べると、
「この人は右寄りなんじゃないか」とか
「愛国心が強いからだろう」
と決めつけられる風潮も少なからず影響してきました。
最近では、テレビやメディアだけでなく、ネットを通じて誰でも情報を得られるようになり、少しずつその考え方にも変化が見られるようになっています。
それでもなお、宗教イコール怪しいというイメージは根深く残っているのが現状です。
こうした歴史的な背景や社会的な動きが、マインドフルネスや瞑想に対する偏見につながっていると言えるでしょう。
オウム事件が与えた瞑想への影響と日本の宗教観
戦後の政策が影響しているのに加えて、オウム真理教事件の影響も大きかったですね。
この事件で、彼らが推奨していた中にヨガや瞑想といった要素が含まれていたため、日本では宗教や新興宗教に対する恐れが非常に強くなりました。
その結果、「宗教イコール怪しい」という価値観や固定観念が定着していったわけです。
しかし、世界的に見ると、宗教を大切にしている人々が大半を占めており、無宗教である方がむしろ少数派なんですね。
実際、宗教を持つことには多くのメリットがあるとされています。
例えば、精神的な安定や、他者とのコミュニケーション能力の向上、人を大切にする心などが挙げられます。
これに対して、無宗教であることのメリットは実はあまり多くないんです。

また、日本では「無宗教」と言われますが、実際には儒教や仏教、神道の価値観が今でも根強く残っていますよね。
例えば、物を大切にする気持ちや年配者を敬う心、人を大切にする文化、そして空気を読むことなど、これらは日本人の根底にある宗教的な価値観そのものです。
それなのに、宗教に対して「怪しい」と感じる日本人が、年始になると初詣に行き、長い行列を作ってお賽銭を投げる姿を目にします。
海外の人から見ると、「それもまた強い信仰の一部だ」と思われるかもしれませんよね。
それでも私たちは、自分たちを無宗教だと思い込んでいるわけです。
このギャップが、日本人の宗教観やマインドフルネスへの違和感をさらに複雑にしているのではないでしょうか。
ジョン・カバット・ジン博士が切り開いた瞑想の新時代
話を少し戻しますが、宗教というもの自体は決して怪しいものではありません。
ただし、そう感じてしまう背景や文化的な影響があるのは事実だと思います。
では、なぜマインドフルネスがそのような文脈で語られるのかというと、これは仏教や禅に由来しているためです。

マインドフルネスを世界に広めたのは、ジョン・カバット・ジン博士という方です。
彼は1980年代にアメリカでマインドフルネスを広げましたが、その前に日本を訪れて瞑想の修行を行い、その効果に感銘を受けました。
彼がアメリカに戻った頃、ちょうど脳科学が急速に発展し始め、瞑想の効果を科学的に証明する研究が進められるようになりました。
瞑想自体は、2000年から2500年前にはすでに世界中でさまざまな形で行われてきたものですが、これを科学的に明確に示したのが彼の研究の大きな功績です。
特に、脳の活動を測定する医療技術の進歩により、瞑想が実際に脳に良い影響を与えることが証明されました。
そして、無料で手軽に実践できる方法として、マインドフルネスは一気に普及していきました。
現在では、マインドフルネスは世界中で広く取り入れられています。
たとえば、ニューヨークの公立小中学校では、毎朝のマインドフルネスの時間が必須科目として取り入れられているそうです。

このような動きは徐々に日本にも波及しており、日本でもマインドフルネスが日常の一部として受け入れられる時代がもうすぐ来るのではないかと思います。
「やってて普通だよね」と言える日が訪れるのも、そう遠くない未来かもしれませんね。
日常生活で取り組める簡単なマインドフルネスの方法
マインドフルネスは仏教を起源としていますが、現代では宗教的な要素を取り除き、トレーニングメソッドとして開発されています。
そのため、宗教観は以前より薄れてきています。
ただし、たとえば「心の平穏を保つ」といった表現には、どうしても仏教由来のニュアンスが含まれており、日本人には少し特別な印象を与えるのかもしれませんね。
しかし、仏教自体は私たちの日常生活に深く根付いているものです。
仏教を「怪しい」と否定してしまうと、自分たちの根底にある価値観や文化を否定することにもつながりかねません。
まずはそういった背景を理解したうえで、マインドフルネスに取り組む価値を考えてみるのも良いのではないでしょうか。
また、ご質問で「簡単に取り組める方法」について触れていただいていましたので、いくつか実践しやすい方法をご紹介します。
たとえば、呼吸瞑想は非常にシンプルです。
呼吸に意識を向けて、吸う息や吐く息をじっくり感じることから始めてみてください。
また、歩行瞑想というものもあります。
これは歩く感覚や、足が地面に触れる感覚、体のバランスを意識しながら歩く方法です。

さらに、掃除をしながらでも練習できます。
雑巾を持つ手の感覚や、布が床を拭く感触に集中してみるだけで、マインドフルネスを実践することができます。
こうした練習方法はどれも特別な道具が必要なく、日常生活の中で手軽に取り入れることができます。
また、朝の時間にこの音声を聞いていただくだけでも、マインドフルネスの一環として役立てていただけると思います。
ぜひ、無理のない範囲で一緒にマインドフルネスを実践していきましょう。
ご質問ありがとうございました。
今日もあなたにとって素晴らしい一日になりますように。
マインドフルネス×潜在意識勉強会はコチラ
↓
ご案内ページへ
※紹介者名欄にJAYブログとご記載いただくと無料で参加できます
JAYへの質問・相談はこちら
↓
フォームページへ